2019年11月11日 10月31日(木)の裁判の報告と、次回の予告。弊社を支援してくださる皆様が裁判所を取り囲んでくださった事に深く感謝。750人中、650人が弊社を応援。
10月31日(木)の第16回期日は弊社を支持し、応援してくださる皆様が裁判所を取り囲むような形でこの日を迎えることができました。この日、貴重な時間を有給休暇を取って裁判所に駆けつけてくださった社員の皆さん、そして、弊社の名誉と国家の存亡がかかっているこの裁判に、弊社と何の利害関係もないのに、国家存亡の危機を感じ取り、弊社を強く支援してくださっている皆様に、心から御礼申し上げます。本当に有り難うございました。
この日、傍聴券獲得に裁判所に集まった人々は、傍聴抽選券の最終番号が749番。そのうち、概数しか分かりませんが、弊社社員500名ほど、弊社社員のご家族や親戚、友人の皆様が100名ほど、それ以外で、いつも弊社を応援、支援してくださっている皆様が50名ほど、併せて弊社側の支援者は650名ほどで、原告側を圧倒していたと思います。
原告側の支援者の方は恐らく100名以下で、裁判所の50席の傍聴席の大半は弊社支援者で占めることができました。原告側で、入廷できた傍聴人は5、6名だったと、原告側の支援団体がご自身のホームページにも書いておられるので、上記の概数はほぼ間違いないと考えられます。
法廷では、原告側は原告1名、弊社側は3名への証人尋問や、本人尋問が行われました。
弊社側の3名とは、弊社を一貫して強く支持してくださっている退職者の方(O氏)の方1名、原告の直属の上司の(E以下敬称略)1名、そして弊社代表取締役会長今井(以下敬称略)の3名です。
弊社側として、弊社代表取締役会長の今井と、同じく代表取締役社長の宮脇(以下敬称略)が、最初から最後まで、弊社代理人弁護士3名の後ろの席に着席していましたが、証言席に座ったのは今井を含め上記3名です。
弊社としましては、この日まで、傍聴を希望する多数の社員に、それを自粛するよう依頼してきたところ、ついにこの日に至り、原告がこの日までに訴えを取り下げなかったことを非常に残念に思っています。
事実として、原告と顔をあわせたのは、会長の今井にしても、社長の宮脇にしましても、この日が初めてでした。
直属の上司を除く、入廷した社員の、ほぼ全員がそうであったと思いますので、原告が証言席に座るまで、どの人が原告なのか、会社側で入廷した者は、ほぼ誰も分からなかったと思います。
これまで社内で5年間、原告がいやな思いをしないように、一切その氏名を関係者以外誰にも伝えることなく、また、その顔を知られる事のないように、会社として最大限の配慮をして参りましたが、その思いやりが原告に理解されなく、非常に悲しく思います。
弊社では「聞けばいいだけ、言えばいいだけ」のシステムが確立されており、に相談しても納得できない事は、どんどんその上の上司に相談して下さり、役職の付いていない社員の意見や、相談を、会長や、社長が直接聞き取る事ができるシステムを確立しています。そして、多数の社員が実際にそうして救われております。
原告は裁判に訴えることなく、直属の上司の答弁で納得できなければ、最後はEの部署の担当役員である会長にお聞きになられたらよかったのに、あるいは裁判を始めてからでも、社員なのですから、いつでもそうできたのに、どうして裁判を始め、その後も取り下げず、この日を迎えたのか、本当に会社として理解に苦しむところです。
裁判の最初に、宣誓があり、原告、及び、弊社側の3人が、裁判において一切虚偽を言わない事を宣誓しました。ただ、原告だけは、名前を述べることを裁判官によって免除されたので、氏名を名乗ったのは弊社側3名だけでした。
原告に対する当方弁護士からの質問で、原告は
「フジ住宅社内で直接、他の社員から差別的なことを言われたり、暴言を浴びせられたりしたことはありましたか?」と聞かれ、
「それは、面と向かって言われたことはありません。」とはっきりと証言しました。
原告はなぜそんなに苦しい職場にい続けるのかとの原告側代理人の質問には
「自分にとって会社は大切で、会社に変わって欲しいから」
「会社が変わってくれないと、私はもっと傷つく」と訴えていましたが、今に至るも会社は原告たちが言う「ヘイトハラスメント」の範囲が理解できないでおります。
この言葉の定義が分からず、原告がいやなものは原告に配るなという要求だと思われますが、もしも、そうして原告にだけ他の全職員に配った情報を伝達しなければ、それも差別だと逆に言われかねません。
さて、原告は「韓国という国に対する批判」や「論評」をも、民族差別であると捉えて、この裁判を起こしているのだという事が、当日の尋問の中でよく分かりました。
例えば当方弁護士の質問
「従軍慰安婦問題について、軍による強制連行がありませんでした、これ、あなたの恐らく意見とはことなりますよね。」という質問に対して
原告は「はい。」と証言しています。
また、当方弁護士が原告の高校時代の事柄について、ネット上に「軍国主義教育をしていると思った」と、原告自身が述べていることに関して、
「高校時代、体育祭の練習で国旗掲揚、国家斉唱があったとき、あなたは立っておれないほどのしんどい気持ちになったと書いておられるが何故か?」との問いに原告は、声が小さく聴き取りにくいですが、こう答えていました。
「予期していなくて、いきなり鳴り出してびっくりしたのと、自分の体が本当についていかなかったからです。」と答え、さらに、「私にとっては、当時、日の丸の君が代も別に国家でも、国旗でもなかったですし、あくまで戦争の時に日の丸を掲げてみたいな、君が代をもとでみたいな、そういうものもあったのかなと思っていて、それをあえて大々的にどんと来たので反応できなかった。」、「あの戦争のときに私の父もですけど、皇民化政策の中で教育を受けてたとかいうのは知っていたので、そういったことを考えたときには、私にとってはやっぱり受け入れにくいものです。」と証言していました。
また、当方弁護士が
「あなたと相容れない価値観とか、文化に接したときに、あなたはしんどくなっちゃうんですね。」と質問したところ「はい。」と原告は証言しました。
それから当方弁護士の、
「あなたが『私を支えてくださる人たち』 と述べておられる中に、フジ住宅をヘイトハラスメント企業とののしって、(そのチラシが入った)ティッシュを街頭で配布している人たちも含むのか?」との問いに、原告が
「はい、含みます。」と証言した事は、ため息をつきたくなるほど哀しく、淋しい事柄であると、大多数の傍聴した社員は感じたであろうと会社は考えています。なぜなら原告は紛れもなく今も弊社の社員であり、他の外国籍の社員を含む全社員とまったく同じ条件で勤務し、同じように福利厚生を受け、このような裁判を起こして会社を批判し、大損害を与えているのに、この5年間、社内で誰からも一言の暴言を浴びせられた事もなく、何の差別も受けていない事を誰もが知っているからです。
さて、退職者O氏の証言で、社内で配布された文書や、書籍について、原告を含む誰であっても、読む事を強制される事はない事も明らかになりました。
退職者は配られた資料や、書籍を、他の人がどれくらい読んでいたかどうかは知らないし、調べたこともないので分からない。
しかし、自分は本当にためになる資料や、書籍ばかりであると感じ、極力全部読んでいた。そのおかげで、どれほど目を開かれ、その後の人生が豊かになり、助けられたか分からない。
ただただ感謝しかない。心から感謝している旨を、繰り返し述べて下さいました。
原告上司のEは、原告が「退職」を勧奨されたと訴えていることに関して、この件は、弊社会長の今井も述べていることだが、退職を強要した事など一切ない事を証言しました。
原告の上司Eは、そもそもが、原告が職場の状態について「しんどい」とご自身の評価コメントに書かれていたので、自分の部下に「しんどい」と訴えている人がいるのに、その状態を放置するのは由々しき問題なので、Eは原告を何とか助けてあげたいと思い、これをそのときの自分の上司であった今井に相談した。今井は、この件で以下のように述べており、Eがその通りで間違いない事を証言しました。
以下、弊社会長今井の陳述です。法廷でも、陳述書に書いてあるのと同じ陳述を致しました。
「この裁判では、原告に対して原告の上司が選択肢を提示したことについて当社による違法な退職勧奨であるとも主張されています。
私の資料配布や教科書関係の呼びかけが原告にストレスになっているのであれば、退職を選んでいただくのもお互いのための一つの選択肢かと思い、それに伴い300万円をお支払いする解決を、原告の上司を通じて当社は提案しました。その金額は、原告にも相応の配慮をしたつもりです。
しかしながら、当社から原告に対し、何度も退職を勧めたり、退職に追いこむような圧力をかけたことはありませんし、そのことは、原告の上司が電話で話されている内容や話しぶりを聞いていただければ、一目瞭然だと思います。」
裁判の最後に 弊社会長今井への本人尋問が双方の弁護士よりありました。
それに先立って、入廷の時、ちょっとした「事件」がありましたので、皆様に報告いたします。
弊社会長今井は、いつも上着の見えるところに拉致問題解決のシンボルである「ブルーリボンバッジ」をつけているのですが、傍聴人の希望者が多数で、抽選が大幅に遅れたため、原告側と、当方の代理人弁護士、原告、被告当事者は、全員先に法廷内に入っていました。
すると裁判所の職員の方が弊社今井に「そのブルーリボンバッジをはずしてください。」と告げに来ました。
弊社今井は、なぜ「ブルーリボンバッジ」をはずさねばならないのか理解できかねるため、それは裁判長のご指示ですかと職員に伺ったところ、「そうだ。」とお答えだったので、裁判長をここに呼んで欲しいとお伝えし、一旦職員の方は裁判長のところへ行かれました。
その後、しばらくして、戻ってこられ
「ブルーリボンバッジをはずしていただけないと開廷できません、と裁判長が言っています」旨を告げられるので、裁判が始められなければ多くの方にご迷惑がかかると今井は判断し、やむなくバッジをはずすという一幕がありました。
これは傍聴人の方がまだ法廷に誰も来ておられないときの出来事ですので、ここにありのままの事実を皆様にお伝えいたします。
今井の法廷内での尋問への答弁は、すべて、このブログに前回アップしてある今井の陳述の通りです。
それをここで書いても長くなるだけですので、ここでは上記のバッジの件や、その他、法廷内の出来事で、注目すべきことだけをお伝えしたいと思います。
さて、原告への尋問のときに、当方弁護士は裁判官から
「裁判と直接関係ない、個人の思想信条に関わる質問はしないで下さい。」との注意を受けました。
また、弊社今井は、原告側弁護士の質問に対し、それを嫌がらず、どんどん受けて、自らの思いを陳述しようとするので、裁判長から、今井にもそれをやめるように何度か注意がありました。
「質問に対し、端的にその答をだけをするように」裁判官は何度も求めていました。
しかし原告側弁護士は繰り返し次々と今井の思想信条についても質問を重ねてきます。今井が答え、そう考える経過を説明しようとすると、裁判官に話を阻止されるので、ついに弊社会長今井は、「そういうことなら」とポケットから、先ほどはずしたブルーリボンバッジを取り出し、
「それでは裁判長、先程はずさせられたこのブルーリボンバッジですが、どうしてはずさないといけないのですか、その理由を端的に一言で答えてください。」と裁判長に今井が迫る場面もありました。
裁判長はその質問に理由は答えず、「裁判所が定めたルールに従ってください。」とのみ答え、なぜブルーリボンバッジをはずさねばならないかの説明はありませんでした。
日本の裁判所の名誉の為に念のために書いておきますが、「法廷内でメッセージ性のあるもの」をはずしてくださいと裁判所が指導される事は間違っていないと弊社は思っております。
また、国旗は法的裏づけがあるので、はずせとは指導されない事は当然ですが、各人がつけている社章や、各種ロゴマークなどもはずすようには一切指導されないのに、ただ、ただブルーリボンバッジのみをはずすように指示されていることには非常な違和感を持っています。
首相はじめ多くの国会議員、地方議員の皆様も常時身につけておられるこのバッジは、言うまでもなく北朝鮮によって拉致された国民を救出する国民の願いの象徴であり、バッジをはずすように訴訟指揮をしておられる中垣内裁判長も法の定めるところにより、拉致問題の解決に努力しなければならない立場にあります。
あらゆる国家公務員は拉致問題の解決に協力しなければならない立場にある事は以下に示す法律に示されており、ブルーリボンバッジそのものに法的裏づけはなくとも、法制化される以前の日の丸が「日本国旗」であったのと同様、ブルーリボンバッジにはすでに国民の総意としての「準法的裏づけ」があると今井は考えているわけで、我が儘を言っているわけではありません。
また、当裁判に傍聴に来ておられる、弊社を応援してくださっている方も、常時「ブルーリボンバッジ」を身につけておられる方が多く、裁判所でそれをはずすように訴訟指揮されることの違和感を、いろいろな場所ですでに述べておられますが、弊社も同様に、入廷に当たって「ブルーリボンバッジ」をはずさなければ裁判を受ける権利を剥奪されるというような事は、本当に異常なことだと思っています。
この裁判所だけでなく、他の裁判所でもこういった事が起これば、それは我が国にとってきわめて重大な事柄であると考えており、この点もここにはっきりと書いておこうと思います。
裁判官も以下の法律を守らねばならないはずです。
法律第九十六号(平一八・六・二三)
◎拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律
(国の責務)
第二条 国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。
この法律に従えば、紛れもなく国の機関であるところの、我が国の裁判所の裁判官も、常に拉致問題の解決に尽力する責務を負っており、少なくともその妨害をするようなことはあってはならないところ、どうして被告がブルーリボンバッジをはずさなければ、開廷できないのか、まったく理解できないところで、これが当社の見解であります。
裁判の終わりのほうで、原告側弁護士が 弊社会長の今井に
「あなたは、先ほどから裁判官の指揮に従わず、裁判官を怒らせるような事をたくさん言っておられるが、そんな事をして裁判に不利になるとは考えないのですか?」
との素朴な質問をしました。
弊社会長の今井は
「あなたの仰る通り裁判には不利になるでしょう。しかし、私は正しい事は正しいと言いたい。」旨を述べ、間違っている事は間違っていると正さなければならないことを伝えました。質問者はそのまま次の質問に移りしました。
以上が当日の報告です。
次回、第17回目の期日は令和2年1月30日(木)です。それが結審となり、遅くとも令和2年夏前には判決が言い渡される見込みです。
皆様、どうぞ今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます。
続きを読む



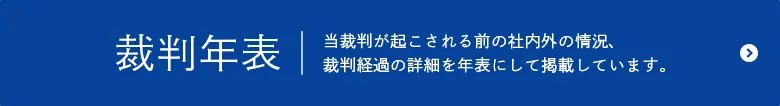
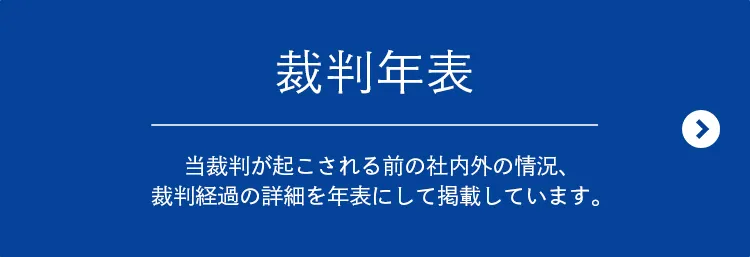

この記事に寄せられたコメント(一部)